核家族化の影響で、以前のようにお墓を維持し継承していきことが難しくなりなした。
そもそも、今のように家族の墓を持つことが一般的になったのは明治以降のことです。
かつては、一部の階級を除いて庶民は遺体を山や海川に捨てるのが普通でした。
しかし、江戸時代から庶民でもお墓を作る欲になり、明治になって伝染病予防のために火葬が普及し始め、現代のように火葬しお墓に納骨することが一般的となりました。
家のお墓を持つようになったのは明治も30年を過ぎたあたりからだと言われています。
こんなこともあり、改めてお墓の在り方について考える人も増えてきました。

お墓事情 先祖祭祀から個人祭祀へ
| 寺院墓地 | 寺院境内で運営・管理している墓地のこと。寺院墓地にお墓を持つには、その寺院の檀家となる必要があります。檀家には、寺院の活動に積極的に参加し、その寺院を支持することが求められます。 |
| 霊園墓地 | 公営と民営があり、公営は比較的安価ですが、数に限りがあります。宗派等は問わないところがほとんどです。 |
| 永代供養墓 | お墓の継承者がいなくても、寺院や霊園が永代に渡る供養・管理を約束してくれるお墓のことで、通常は生前の申し込みも可能です。 一般的に他の人と一緒の墓、あるいは同じ納骨堂に納骨されることから、「合祀墓」「合同墓」「共同墓」などとも呼ばれます。 |
| 納骨堂 | 遺骨を収蔵する施設のことです。かつては、お墓を建てるまでの間、一時的に遺骨を納める意味合いが強かったようですが、現在は永代に渡る供養を前提とした墓所としての需要も高まっています。 ロッカー式:ロッカー状の納骨棚に骨壷を納めます 仏壇式:上部が仏壇作り、下部に納骨する形状の納骨堂です。 自動搬送式:参拝口や礼拝室に専用のカードをかざしたりIDを打ち込んだりすると、自動で遺骨が呼び出される形式です。 |
| 散骨 | 遺骨を自然に返す「散骨葬」が増加しています。散骨とは、亡くなられた方の遺骨をお墓に納めず、海や川などへ撒くこと。その形は、海や川、山中や野山、そらや宇宙に散骨するなど多様化しています。 ※散骨の方法や散骨のできるエリヤについては専門家にお問い合わせください。 |
今まで多かったのが寺院墓地です。
その寺の檀家となるため檀家としての役割を担うことが条件となります。
宗派が異なればそこの墓に入ることはできません。
お寺への関わりや費用の負担も多いことから、昨今の核家族化で檀家制度も少なくなってきています。
そこで、檀家制度のない霊園にお墓を持つ人も多いようです。
好きな場所にある霊園に好みの墓を建てることができます。
ただし、場所によってはかなりの高額となります。
さらに最近では、お墓参りできない人に変わって、あるいはお墓参りしてくれる人がいなくても、代わりにお寺が責任を持って永代に渡って供養と管理をしてくれる永代供養墓を選ぶ人が増えてきました。
一般的に他の人と一緒の墓あるいは同じ納骨堂(棚)に安置されることから、合祀墓、合同墓、合葬墓、共同墓、集合墓、合葬式納骨堂などとも呼ばれています。
一般のお墓(先祖代々のお墓)との違いはお墓参りしなくてもお寺が責任を持って永代に渡って供養と管理をしてくれる、墓石代がかからない(個人墓の場合を除く)、墓地使用量が割安になるなどで、一般のお墓と比べ料金が安く、一式料金を一度払えば、その後の管理費用、お布施(お塔婆代など)、寄付金など一切費用はかかりません。
過去の宗旨・宗派は問われませんし、宗旨・宗派にこだわる必要はありません。
お墓に拘らないという人にお墓に代わる葬法方法として広まりつつあるのが、自然に還ろうとする自然葬です。


自然葬とは主に、遺骨を粉末化したのち、それらを海や川に幕散骨という方法を指します。
その中でも、海に散骨する海洋散骨を選ぶ人が多いようです。
陸地だと限られた場所でしか散骨できませんが、海の場合は陸からある程度距離があり、漁業に影響のないところであれば散骨が可能です。
宇宙にロケットで散骨する宇宙葬などもあります。

このほか、小さな容器やペンダントに個人の遺灰や髪の毛などを収め、自宅に置いたり身につける手元供養があります。
お盆やお彼岸にお墓参りに行く風習が日本にはあります。
いわゆる遺族が故人を偲ぶ拠り所です。
自分だけでなく、家族とともにお墓をどうするかは考えたいものです。
墓じまい
「墓じまい」とは、墓を守る跡継ぎがいない、お墓のある場所が遠くてなかなかお墓参りに行けないといった方が現在の墓を撤去し、近くの墓地や永代供養墓地に移転したり、海洋葬や樹木葬など自然葬にすることをいいます。

墓地に埋葬されているご遺骨を他の場所や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬には、所定の手続きが必要となります。
移転先の墓地の管理者から「受入証明証」を発行してもらいます。
⬇️
現在埋葬されている墓地の管理者から「埋葬証明書」を発行してもらいます。
⬇️
墓地のある市区町村役場に改葬届を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
⬇️
改葬元墓地の管理者に「改葬許可証」を提示し、ご遺骨を取り出します。
⬇️
墓石の「御魂抜き」の法要を行います。
「御魂抜き」とは、お墓から仏様の魂を抜いて元の石の状態に戻す「閉魂法要」のことをいいます。
⬇️
改葬先墓地の管理者に「改葬許可証」を提示し、ご遺骨を埋葬します。
その際、墓石の「開眼供養」を行います。
※改葬許可証の有無は地域により異なりますので事前にご確認ください。
お墓に関する費用
◯お墓の費用ってどれくらいかかるの?
- 新しくお墓を建立する場合:100万〜300万※永代使用料+墓石工事費+管理費を含む
- 先祖代々のお墓の引っ越し:50万〜150万※墓地代は別
- 永代供養納骨堂:50万〜200万
- 永代供養墓ち:30万〜200万
- 樹木葬:10万〜100万
- 散骨:5万〜30万※チャーター、合同、代行委託で金額が変動








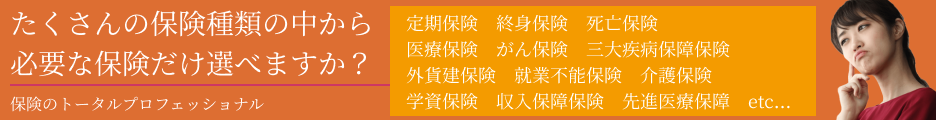



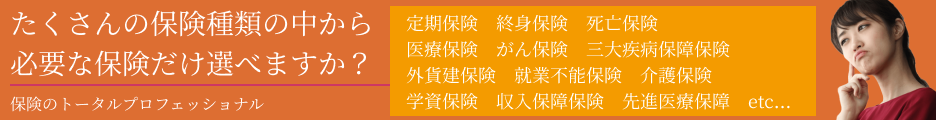











コメント